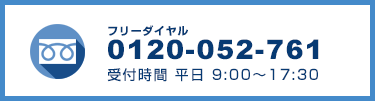オフィシャルブログ
プラスチックを原点に戻って考え、その将来は?
プラスチックの定義とは
私たちが日常的に利用しているプラスチックには、JIS(日本産業規格)による明確な定義があります。それによると、プラスチックとは「高分子物質(主に合成樹脂)を主原料として人工的に有用な形状に成形された固体」を指します。ただし、繊維やゴム、塗料、接着剤などは除外されています。つまり、単に人工的な素材であればプラスチックと呼べるわけではなく、一定の条件を満たす必要があるのです。
プラスチックとゴムの境界線
補足的に整理すると、プラスチックには次の特徴があります。
- 高分子(壊れにくい大きな分子の集合体)を原料とすること
- 人工的に形作られた固体であること
- ゴムや繊維などは含まれないこと
ここで気になるのは「ゴムは含まれない」という点です。天然ゴムとプラスチックは確かに異なるものですが、両者の間に位置する「エラストマー」という素材はどちらに属するのでしょうか。エラストマーとは石油を原料とし、弾性をもつ材料の総称です。
エラストマーの扱いについて
エラストマーには厳密な定義がなく、一般的にはゴムも含まれると考えられています。しかし業界では、ゴムを除いた材料をエラストマーと呼ぶ場合が多いのです。代表的なものにはTPU(熱可塑性ポリウレタン)やTPE(熱可塑性エラストマー)があります。さらに、軟質ポリ塩化ビニル(軟ビ)も柔らかく弾性を持ち、TPUやTPEに近い風合いがありますが、こちらは明確に「プラスチック」として分類されています。そう考えると、エラストマーも広義には樹脂の仲間といえるのではないでしょうか。
高分子という共通点
エラストマー、軟質ポリ塩化ビニル、さらには合成ゴムも、いずれも高分子材料です。このように境界線を厳密に引こうとすると「どちらに分類すべきか」という疑問が次々に出てきて混乱してしまいます。しかし、こうした「重箱の隅をつつく」ような視点こそが、新しい発見や革新的な開発につながる可能性があると考えると、むしろ面白い領域だといえるでしょう。
石油とプラスチック、そして地球環境
話を戻すと、プラスチックの多くは石油を原料にしています(一部は天然ガスから作られるものも存在します)。一方で、化石資源を効率的に再利用しようとする取り組みが進む一方、「石油はまだまだ枯渇しない」という考え方もあります。さらに、紙やプラスチック、金属のリサイクルには多くの熱エネルギーが必要ですが、そのエネルギーの大半は依然として石油や石炭といった化石燃料に頼っています。結局のところ、地球にとって何が最適解なのかは簡単に答えが出せるものではありません。ただ、効率的に資源を活用する重要性は改めて強く認識する必要があるでしょう。
想像する未来
宮崎駿監督の『風の谷のナウシカ』では、人間の活動によって荒廃した地球が描かれています。フィクションではありますが、私たちの未来にまったく無縁とは言い切れません。プラスチックをはじめとする高分子材料の扱い方は、人間と地球の共存を考える上で大きなテーマであり、これからも議論や研究が続いていく分野だといえるでしょう。