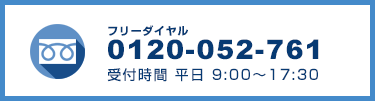オフィシャルブログ
プラスチック、ゴム 材料の代表的な製造方法
樹脂やゴムの製造方法は、定義によって厳密に定められたものではなく、各企業の開発によって進化してきたものです。明確な決まりがあるわけではありませんので、ここでは大まかにカテゴリごとにまとめました。
大きく分けると、射出成形(インジェクション)と押出成形の2種類に分類されます。
よく「せいけい」という言葉を使う際、どちらの漢字を用いるのか?という疑問があると思いますが、JIS(日本産業規格)では「成形」という表記を使用しています。そのため、ここでは「成形」で統一します。
なお、「成型」という表記も、金型を使用して作る場合には用いても問題ないと考えています。メーカーによっては、意図的に「成型」という表記を採用している場合もあります。
射出成形
樹脂(プラスチック)において、最も多く利用されている製造方法です。部品などを作る際によく使用され、複雑な形状の成形にも対応できます。20年ほど前の技術と比較すると、樹脂の流体力学の研究が進み、より精密な形状を作ることが可能になっています。
金型から取り出された製品は、プラモデルの部品を切り取る前の状態を想像していただくと分かりやすいでしょう。ひとつの金型で複数の部品を同時に成形することもできます。
押出成形
液体状になった樹脂やゴムを口金(ダイス)から吐出させ、連続的に製品を成形する方法です。
-
Tダイ法
平面状に広く引き伸ばす製法で、厚めのシート製品によく使用されます。
成形機の形状がアルファベットの「逆さまのT」に似ていることからこの名称があり、また洋服を吊るすハンガーにも似ていることから「ハンガーダイ」とも呼ばれています。 -
インフレーション
吐出部分(ダイ)の構造はTダイ法と似ていますが、吐出した樹脂を空気で膨らませ、円筒状に広げる方法です。ポリ袋や高発泡シートを製造する際によく用いられます(高発泡シートの場合、横向きで成形するケースもあります)。
円筒状に成形されるため、切れ目を入れて1枚のシートにしたり、二重構造にしたり、ポリ袋のように円筒のまま利用するなど、様々な製品形態に応用されています。 -
口金成形
吐出部分に異形の口金を設置し、棒状・ひも状などの断面形状を持つ製品を成形する方法です。上記のシート状製品と異なり、吐出時の熱を冷却するための設備が必要になることもあります。
また、発泡製品の場合は、吐出時に大きく発泡するよう設計されているケースもあります。ゴムを成形する場合は、吐出時にはまだ架橋(加硫)されていないため、吐出後に熱をかけて加硫させる工程が必要になる場合もあります。